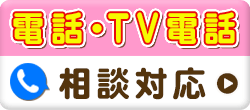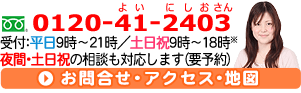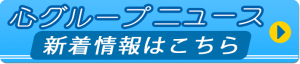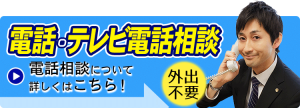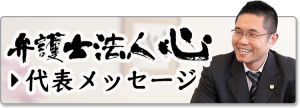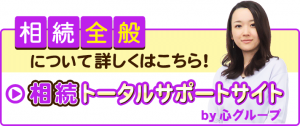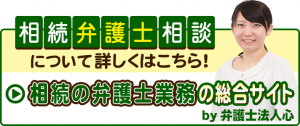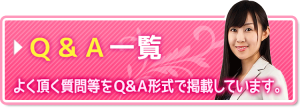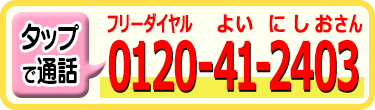相続放棄の流れ
1 概要
相続放棄の申述は、申述書などの書類を準備し、管轄の家庭裁判所に提出して進行する手続になります。
本稿では、相続放棄の申述手続の流れについて、準備段階も含めてご説明します。
2 戸籍類の準備
相続放棄の申述を行うためには、まず、①被相続人の死亡とその時期、②被相続人の最後の住所地、および③被相続人の相続人であること、以上3点がわかる資料提出しなければなりません。
例えば、被相続人が父、相続人が結婚して両親の戸籍から出ている子である場合、①父の死亡が記載されている戸籍または除籍謄本、②父の最後の住所地が記載されている除住民票または戸籍の除附票、③子の戸籍謄本または抄本が必要になります。
第2順位や第3順位の血族相続人の場合は、提出する戸籍等の量も多くなり、取得する作業にも時間がかかりますが、熟慮期間の3か月の満了が迫っている場合は、とりあえず申述書と揃っている戸籍等を裁判所に提出して申立てを行い、不足している戸籍等は取得次第提出することになります。
3 その他の資料の準備
相続放棄の熟慮期間は、被相続人の死亡および自分が相続人になったことを知った時から3か月ですが、被相続人の死亡から3か月が経過している場合は(被相続人と疎遠だった場合、被相続人が死亡したことを知らないことも多いです)、被相続人の死亡および自分が相続人になったことを知った時期について、疎明資料(例えば被相続人の債権者から相続人宛てに届いた請求書など)を提出するのが通常です。
このような資料も準備する必要があります。
4 申述書の作成と提出
資料が一通り揃いましたら、申述書を作成し、必要な収入印紙や切手を添付して管轄の家庭裁判所に提出します。
管轄の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
5 照会書の提出
多くの家庭裁判所では、相続放棄の申述書が提出された場合、申述人本人宛に照会書を送付します(一部の家庭裁判所は、弁護士が代理人として一定の書面を提出した場合は、申述人本人に照会書を送らない扱いをしています)。
照会書が届きましたら、回答を記載し、同封されている返信用封筒で裁判所に返送することになります。
弁護士や司法書士に相続放棄の手続きを依頼している場合は、回答を記載するにあたり、必ず、依頼している弁護士等に回答の書き方を確認してください。
また、依頼していない場合でも、わからない点があれば専門家に相談するとよいでしょう。
6 相続放棄申述受理通知書の送付
申述書等の記載や添付資料、また熟慮期間など相続放棄の要件に不備がなければ、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理する審判を行うことになります。
申述が受理されますと、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が申述人本人または代理人宛てに送付されます。
被相続人の債権者からの請求等に対しては、この相続放棄申述受理通知書のコピーを当該債権者に送付することで足りることがほとんどです。
7 相続放棄申述受理証明書
別の相続人が相続手続き(相続登記など)を行うために必要な場合等には、相続放棄申述受理証明書の発行申請を家庭裁判所に行うことになります。
以上が、相続放棄手続きの基本的な流れになります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒251-0052神奈川県藤沢市
藤沢973
相模プラザ第3ビル2F
0120-41-2403